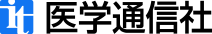はじめに
受験対策のキーポイント
第61回診療報酬請求事務能力認定試験の結果について
公益財団法人日本医療保険事務協会(理事長・滝澤秀次郎)が,2024年12月15日(日)に実施した第61回診療報酬請求事務能力認定試験の結果は,次のとおりです。
| 受験申込者数 | 2,913人(医科:2,863人 歯科:50人) |
| 受験者数 | 2,633人(医科:2,594人 歯科:39人) |
| 合格者数 | 1,083人(医科:1,069人 歯科:14人) |
| 合格率 | 医科:41.2% 歯科:35.9% |
第62回診療報酬請求事務能力認定試験の実施について
診療報酬請求事務に従事する者の資質の向上を図るため,次のとおり全国一斉統一試験を実施します。
| 1.受験資格 | 問いません | |
| 2.受験科目 | 医科,歯科のいずれかを選択 | |
| 3.出題範囲 | (1) 学科試験 | ①医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 ②保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 ③診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 ④医療用語及び医学・薬学の基礎知識 ⑤医療関係法規の基礎知識 ⑥介護保険制度の概要 |
| (2) 実技試験 | 診療報酬請求事務の実技 | |
| ※法令等(点数表を含む)は,2025年4月1日現在施行されているものとする。 | ||
| 4.試験日時 | 2025年7月13日(日) 午後1時~4時 | |
| 5.試験地 | 札幌市,仙台市,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟市,金沢市,静岡市,愛知県,大阪府, 岡山市,広島市,高松市,福岡県,熊本市,那覇市 | |
| 6.受験手数料 | ¥9,000(消費税込) | |
| 7.受験申込(願書提出)手続 | 〈インターネットによる受験申込〉(※第55回試験から出願方法は,原則インターネットのみとなりました) 2025年4月10日(木)10:00~ 5月23日(金)17:00(予定) ※手続方法等詳しくは日本医療保険事務協会ホームページをご覧下さい。 |
|
| 8.合否発表 | 2025年9月19日(金) | |
| 問合せ先 | 公益財団法人 日本医療保険事務協会 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-3 児谷ビル 電話 03(3252)3811 FAX 03(3252)2233 URL http://www.iryojimu.or.jp |
|
試験の出題傾向と具体的攻略法を考えよう
1.出題の傾向
| 1.医療保険制度等 | 270題(8題) | 16.処置 | 258題(7題) |
| 2.公費負担医療制度 | 25題 | 17.ギプス | 6題 |
| 3.保険医療機関等 | 78題(2題) | 18.手術 | 249題(6題) |
| 4.療養担当規則等 | 267題(3題) | 19.輸血 | 19題(1題) |
| 5.初診・再診 | 369題(7題) | 20.麻酔 | 125題 |
| 6.入院 | 497題(8題) | 21.放射線治療 | 117題(1題) |
| 7.入院時食事療養費 | 73題 | 22.医療材料 | 47題(1題) |
| 8.医学管理等 | 428題(8題) | 23.診療報酬請求事務 | 66題(1題) |
| 9.在宅医療 | 271題(4題) | 24.DPC | 4題 |
| 10.検査 ・病理 | 458題(6題) | 25.医療用語 | 41題 |
| 11.画像診断 | 193題(3題) | 26.医学の基礎知識 | 10題 |
| 12.投薬 | 196題(4題) | 27.薬学の基礎知識 | 10題 |
| 13.注射 | 183題(2題) | 28.医療関係法規 | 74題(1題) |
| 14.リハビリテーション | 247題(5題) | 29.介護保険制度等 | 57題 |
| 15. 精神科専門療法 | 167題(2題) |
2.具体的攻略法
この認定試験は「学科問題」&「実技試験」からなり,配点の詳細は明らかにされてはいないが,試験の合否は学科問題と実技問題の平均点ではなく,学科問題・実技問題それぞれに合格ラインを超えなければ晴れて合格とはいかない。つまりは,バランスのとれた学習をしなければ合格への道は閉ざされるというわけだ。
試験合格のための重要ポイント!
まずは,試験の範囲(ガイドライン)の項目につき,全体の概要や基本的な知識を自分のものにすること。いくら参考書等が持ち込みOKとはいっても,やはりある程度の基礎知識は身につけよう。とくに実技試験においては,このことが大きく差を分けることにもなりかねない。
そのためにはど~すればいいの?
医療事務に関する各種解説書を読み,実技に関しては実例をもとにレセプト作成の練習を重ねよう!(医学通信社の本が役に立つよ!) 最後に,いざ試験に対したとき,まず落ち着いてその問題が何に関するのか,またどの法制度に関するのか,点数表でいえばどの項目なのかを把握することが肝要だ!それにやはり,理解する能力を身につけることだ。とくに点数表の読み解き方は十二分に練習しよう!これさえマスターすれば,試験の8割~9割はできたも同然だ! そのためには,解説書だけでなく,数多くの練習問題をこなし,点数表の使い方を実戦的に身につけよう!そうすれば,恐いものなしだ!(たぶん)
ガイドラインに沿った実戦対策
(1)医療保険制度等
まずは,わが国の医療保険制度の全体の概要を理解しましょう。そしてのちに医療保険各法,とくに「健康保険法」を重点対象として,給付の概要と要件,給付内容などにつき基本的ポイントを把握しておきます。また,実際の試験に当たって最も大切なポイントは,その出題内容がどの法制度に関するものなのか,どの本を調べればよいのか,を把握することです。
過去61回の出題数は270題で,1回の試験当たり4~5題が出題されています。これまでの「頻出項目」は,高額療養費,出産育児一時金,保険外併用療養費――などです。
【参考図書】◆「医療関連法の完全知識 2025年版」(2025年4月刊)医学通信社
(2)公費負担医療制度
特定の疾病を対象として,医療費の一部もしくは全部が公的費用により負担される制度のことです。
この制度は,それぞれの法によって定めが違うため複雑で,対策が立てにくい分野です。過去61回の出題数は25題と少なめですが,ときに1,2題は出題されるため,要注意といえます。
重要なポイントは,感染症法・精神保健福祉法・生活保護法の❶申請手続き,❷給付内容,❸医療保険との関係などです。また,感染症法や難病医療費助成制度のように,近年,大きな制度改正が行われたものは注意が必要です。
【参考図書】◆「公費負担医療の実際知識 2025年版」(2025年4月刊)医学通信社
(3)保険医療機関等
保険診療を行うためには,保険医療機関としての指定が必要であり,医師も登録が必要です。また,保険薬局,特定機能病院,療養病床など,それぞれの定めにより,承認や許可を必要とします。この指定や承認に関する要件を規定している医療法などが主な出題対象となっています。
過去61回の出題数は78題です。
こうした要件や基準を調べる方法,どの本のどの部分に掲載されているのか――を確実に把握しておく必要があります。
【参考図書】◆「医療関連法の完全知識 2025年版」(2025年4月刊)医学通信社
(4)療養担当規則等
【参考図書】◆「診療点数早見表(2025年4月増補版)」(2025年4月刊)医学通信社
(5)診療報酬等
過去61回の全出題数の約7~8割を占めている最重要項目です。なかでも,❶入院,❷検査・病理,❸医学管理等,❹初診・再診――などが「頻出項目」となっています。2024年の診療報酬改定により変更のあった項目や新設項目だけでなく,それ以降の通知で変更があった点にも注意しましょう。
「診療報酬点数表」を十分に使いこなすだけの知識,テクニック,経験が求められます。とくに「注」や「通知」など細部の規定に関しての問題がほとんどなので,あいまいな規定に関する正確な解釈,確実で迅速な検索など,点数表の読み解き方に精通しておく必要があります。
【参考図書】◆「診療点数早見表(2025年4月増補版)」(2025年4月刊)医学通信社
◆「診療報酬・完全攻略マニュアル 2025年4月補訂版」(2025年4月刊)医学通信社
◆「入門・診療報酬の請求 2024−25年版」(2024年7月刊)医学通信社
(6)薬価基準・材料価格基準
薬価基準は,保険診療で使用できる医薬品の範囲と価格を定めたものであり,材料価格基準は,点数表で定められた特定保険医療材料料として算定できる医療材料の範囲と価格を定めたものです。
材料価格基準に関する過去61回の出題数は47題。(薬価基準については,「診療報酬等」のなかの「投薬」「注射」等の項目に分類)
【参考図書】◆「診療点数早見表(2025年4月増補版)」(2025年4月刊)医学通信社
(7)診療報酬請求事務
レセプトの記載方法や請求方法に関する出題です。レセプト作成上の一般的事項や具体的な記載方法については,厚生労働省の保険発通知「診療報酬請求書等の記載要領等について」に規定されています。実技試験におけるレセプト作成には欠かせない規定であり,その基礎的知識だけは身につけておきたいところです。そのためには,この規定に従って実際にレセプトを作成する練習が重要です。学科試験についても,診療報酬明細書に関する過去61回の出題数は66題あります。
【参考図書】◆「診療点数早見表(2025年4月増補版)」(2025年4月刊)医学通信社
◆「診療報酬・完全攻略マニュアル 2025年4月補訂版」(2025年4月刊)医学通信社
◆「入門・診療報酬の請求 2024-25年版」(2024年7月刊)医学通信社
(8)DPC
診断群分類(DPC)点数表の概要や,出来高算定との関係などが問われます。DPC対象病院が増加していることもあり,試験でも出題が増える傾向にあります。
【参考図書】◆「DPC点数早見表(2025年4月増補版)」(2025年4月刊)医学通信社
(9)医療用語
診療報酬の請求に必要な用語として,カルテに記載されている疾患,検査,手術の略称などが問われています。過去61回の出題数は41題ですが,第12回試験以降は出題されていません。
しかし,学科・実技試験全般にわたって医療用語の知識が問われるため,試験に当たっては,検査・疾患・手術・画像診断・医薬品・特定保険医療材料などに関する略語集が必携です(「受験対策と予想問題集 2025年版」“実戦知識のキーポイント”に主要略語の一覧表を掲載)。
【参考図書】◆「最新・医療用語4200」(2019年4月刊)医学通信社
◆「臨床・カルテ・レセプト略語事典」(2015年4月刊)医学通信社
(10)医学の基礎知識
診療報酬に係る一般的な医学知識が問われます。過去61回の出題数は10題と少ないのですが,第14回試験と第20回試験においては4題ずつ出題されています。今後も出題の可能性はあると考えておいたほうがよいでしょう。
(11)薬学の基礎知識
過去61回の出題数は10題。なかでも,処方の際の略号(例;n.d.E.など)は3回出題されているので,その略号表は試験の際には必携です(「受験対策と予想問題集 2025年版」“実戦知識のキーポイント”に一覧表を掲載)。そのほかには点数表の「投薬」の部の通知に規定されている事項が多いので,まずは点数表で調べてみるとよいでしょう。
【参考図書】◆「診療点数早見表(2025年4月増補版)」(2025年4月刊)医学通信社
(12)医療関係法規
医療に関するさまざまな法律の基礎知識が問われます。過去61回の出題数は74題。これまでは医療従事者の資格と業務に関する出題が多くなっています。
【参考図書】◆「医療関連法の完全知識 2025年版」(2025年4月刊)医学通信社
(13) 介護保険制度
第13回試験から新たに出題項目とされました。以後49回の出題数は57題。制度の概要や,医療保険と介護保険の給付調整などが問われます。地域包括ケアシステムが推進され,医療と介護の連携が進むなかで,今後も2題程度は出題されると考えておくべきでしょう。
【参考図書】◆「介護報酬早見表(2024-26年版)」(2024年6月刊)医学通信社
実技試験の実戦対策
実技試験におけるレセプト作成には,やはりある程度の経験が必要になります。したがって,「受験対策と予想問題集 2025年版」などにより例題を数多くこなし,実戦力を身につけることが大事です。
実際の試験に当たっての具体的な手順と留意事項は以下のとおりです。
(1)まずは「施設の概要等」や「職員の状況等」の前提条件が意味することを,点数表により確実に読み取ることです。診療時間・看護体系・医師数・薬剤師・所在地などを確実にチェックします。
(2)カルテに記載されている保険者番号・氏名・年齢・傷病名・診療実日数・転帰などを確認しつつ,レセプトに確実に転記します。
(3)具体的診療行為について全体を把握したのち,個々の診療行為・薬剤等につき,点数表と薬価基準等に従い順を追って算定し記載していきます(電卓等の計算機を持参することを忘れないこと)。
(4)実技・学科ともに終わった後にまだ時間が余るようであれば,カルテの診療項目とレセプトの記載を突き合わせて,算定漏れはないか,計算ミスはないか,もう一度確認しましょう。この確認作業は必ず最後に余った時間でやるようにします。
試験合格者の声
実際に受験し合格した人に,その要領や秘訣を聞いてみました。参考にしてね!
Q:学科問題と実技問題のどちらから先に取りかかったほうがよいでしょうか?
A:レセプト作成は選択式でなく記述式のため,必ず一定時間以上を要し,なおかつより多くの時間を要します。 したがって実技問題を先にしたほうがよいと思います。
Q:持ちこみ資料はどの程度もっていったらよいのでしょうか?
A:時間の制約があるので,そう多くてもむだです。分野別に要点がよくまとまった使い慣れた参考書が6,7冊あれば十分ではないでしょうか。 また,重要ポイントや検査の略称などについては,よくまとまった一覧表をコピーして,自分なりに小冊子にまとめておくと便利です。
Q:実技問題は実務経験者が有利と聞きますが?
A:実務経験者が有利なのは間違いありませんが,そう難解な問題でもないので,例題などで力をつけておけば十分対応可能です。
Q:点数表の通知文など細かい規定に関する問題が多いようですが,どのように対応したらよいのでしょうか? それらを覚えていないといけないのでしょうか?
A:全文暗記は不可能ですから,点数表や参考書のどのあたりに何が載っているかを,ガイドラインとこれまでの出題傾向に沿ってチェックしておく必要があります。そしてその個所に付箋などを付けておくのも有効かと思います。とくに点数表には精通・習熟しておく必要があります。探したい項目がすぐに引けるようでないと,合格はむずかしいんじゃないでしょうか。
Q:実際に試験問題を解くうえで,何かコツのようなものがあるのでしょうか?
A:解けない問題にあまり時間をかけ過ぎないことです。これまでの既出問題で模擬試験をしてみて,だいたいの時間配分を決めておくとよいでしょう。
資料:診療報酬請求事務能力認定試験ガイドライン
診療報酬請求事務を正しく行うのに必要な能力を認定するために,次に掲げる事項について試験を行う。
1.医療保険制度等
(1) 被用者保険,国民健康保険,退職者医療及び後期高齢者医療などについて,それぞれの保険者,加入者,給付,給付率等制度の概要についての知識
(2) 給付の内容すなわち現物給付及び療養費についての知識と,給付の対象外とされるもの,給付が制限されるものについての知識
2.公費負担医療制度
生活保護法,精神保健福祉法,障害者総合支援法,感染症法等法律に基づく公費負担医療制度及び特定疾患治療研究事業等によって患者の医療費負担が軽減される制度についての知識
3.保険医療機関等
4.療養担当規則等
5.診療報酬等
(1) 診療報酬点数表(医科,歯科,調剤)は保険医療における医療行為の料金表であり,診療報酬の算定にあたり種々の取決めがあるが,その算定方法についての知識
(注) ア)基本診療料の施設基準等(令和2年3月厚生労働省告示第58号)
イ)特掲診療料の施設基準等(令和2年5月厚生労働省告示第214号)
ウ)厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成26年3月厚生労働省告示第199号)――等を含む。
(2) 入院時食事療養及び入院時生活療養の費用の額を算定するための知識
6.薬価基準,材料価格基準
保険医療で使用される医薬品及び医療材料の価格とその請求方法についての知識
7.診療報酬請求事務
診療報酬請求書及び診療報酬明細書を作成するために必要な知識とその実技
8.医療用語
診療報酬請求事務を行うために必要な病名,検査法,医薬品等の用語及びその略語の主なものの知識
9.医学の基礎知識
主要な身体の部位,臓器等の位置及び名称(解剖),それぞれの機能(生理),病的状態(病理)及び治療方法についての基礎知識
10.薬学の基礎知識
医薬品の種類,名称,規格,剤形,単位等についての基礎知識
11.医療関係法規
医療法による医療施設(病院,診療所等)の規定及び医師法,歯科医師法等の医療関係者に関する法律による医療機関の従事者の種類とその業務についての基礎知識
12.介護保険制度
保険者及び被保険者,給付の内容等制度の概要についての知識